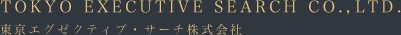社 長 コ ラ ムCOLUMN
賃金テーブルのバランスは崩すべきもの
今や終身雇用、年功序列、豊富な退職金積み立てという雇用における通称「三種の神器」がすでに死語になって久しくなりました。今回はこのなかから特に年功序列にスポットを当てて考えてみたいと思います。
もともと日本には大企業を中心とした独特な終身雇用の考え方がありました。それは若い時に低賃金で苦労して、それでも一生懸命はたらいて会社に丁稚奉公するというものです。そして年を重ねてキャリアの後半になり、高い生産性やパフォーマンスを発揮できなくなったとしても、若い頃のご奉公に会社が報いるかたちで、厳しい信賞必罰を行わず、一定のポストと高い賃金を保証してくれました。このような仕組みが年功序列制度の基本となってきたわけです。これは言うに及ばず短期で人が辞めないことを性善説として設計された制度です。長く勤めれば給料は上がってきますし、在職期間が長ければ長いほど定年退職時の退職金がたくさん受け取れます。長く勤めないとポストが上がりませんから、企業も日本経済もある程度自然に成長していくことが前提になっています。要は対前年比で会社が確実に成長していって、いろいろなコストを吸収していくわけです。そうなるとポストが豊富に生まれ、団塊の世代のような人手が多い時でも、吸収できる余力ができます。こういうことが歴史的背景としてありました。ですから会社を辞めれば不利になるわけです。早いうちに辞めてしまえば、それだけ不利になってしまいます。次にどこかの会社に入ったとしても外様扱いされ、長く働いてきた恩恵に預かれないという、そういう現実が人材の流動性を阻害してきました。歴史を振り返るような話になりましたが、現在はこういう仕組みが完全に崩壊して久しくなってきているわけです。ということで非常に混沌としているため、人によっては大変なカオスと感じる場合もあるでしょうし、あるいは非常にチャンスがあると感じる方もおられると思います。
最近は一部のクリエイティブ(エンジニア、デザイナー、IT技術者など)のみなさまのなかで、新卒の初任給が年俸換算700万円から1,200万円というような会社の存在もめずらしくなくなってきました。このように年齢やポストに関係なく、活躍に応じた評価を適切にしようとすると、過去にベースとなってきた評価制度というのは無用の長物になってしまいます。というより、むしろ阻害要因になってしまいます。しかし日本に長く染みついた度合いはともかくとして、長幼の序をわきまえるいわゆる年功序列的な考え方を急激に180度転換するということは、年配の方だけでなく若い方にも一定の抵抗があるようです。そのために制度設計を現代風にアレンジすることには、どの会社も多大な苦労をしているようです。やはり長年染みついたものを根底から変えるというのは大変なパワーを擁することで、それはどのような事象でも同じことなのでしょう。
では日本の進むべき道はどこにあるのでしょうか。我が国はすでに成熟国家となっています。現状として「政治がリーダーシップをとった新しいビジョン」に基づいた国家像や経済像が明確になっているわけではありません。1年間に40万人以上という人口減少も歯止めがかからない状態が続いているわけで、確実に低成長の時代になっています。この低成長というのは、毎年同じような努力をしているだけでは、状況がどんどん悪くなっていくということを指します。こういう時代に高い業績を上げ続けるには非常に高いレベルでの努力や成果が求められるので、すべての人が望ましい結果を出せるわけではありません。それと同じように毎年均等に努力しても状況が悪化する人のほうが相対的に多くなるわけです。ですからマイナス成長のごとく厳しいと言い換えられることになります。
このようにどの企業も生き残りを賭けたサバイバルのなかに身を置くことになります。以前のように多くの従業員を均等に抱えていく力をほとんどの会社が持ち合わせていません。非常にわかりやすい例ですが、例えば100万円のボーナス原資があったとします。これを10人の従業員で分ける場合、かつての日本は10万円×10人とまでは言わないまでも8万円から12万円くらいの範囲で評価を何段階かに分けて支給するというのが基本的な考えでした。それが直近では100万円の原資のうち80万円を上位2人が受け取り、残り20万円を8人で分けるという、こういったことが至極あたりまえになってきました。こうして一部の幹部候補となりうるスターの人材をつなぎ留め、併せてモチベーションアップにつなげ、華々しい活躍をしてもらうのです。残念ながらローパフォーマンスと判断された従業員には自然退職を促すとともに、場合によってはAi時代のなかで従業員数の自然減を目論むような状況です。残酷なようですがこういったサバイバルの時代に突入しています。
したがって賃金テーブルは議論の結果を待たずして「変化せざるを得ないもの」と心得ておくべきでしょう。人事の分野には進歩的であるよりも保守的な人物のほうが多いものです。すぐには変化を感じにくいかもしれませんが、これから5年程度で急速に先の例のような信賞必罰がはっきりした評価制度の運用がめずらしくなくなってくるでしょう。みなさまもご自分のキャリアをどうするのか、現職の会社とこれからどう向き合っていくのかなど、一人ひとりの自覚が大切になってきている時期に入っているといえます。さて、準備はいかがでしょうか。