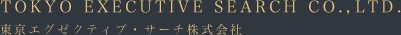社 長 コ ラ ムCOLUMN
顧問が生き残る方法
ある特定の領域で有識者として高い知見を持ち、優れた能力を発揮してきた人物がハイキャリアになると、やがて「上がり」の立場になる時が来ます。会社としては過去の個人的なネットワークを活かしてお力をお貸しいただきたいと声を掛けます。それに呼応して顧問というポジションに就かれる方がシニア中心に多くいらっしゃいます。そこではいろいろなエピソードがありますが、今回はそういう方々が「生き残る方法」にピントを絞ってお話ししたいと思います。
結論から申し上げますと、顧問に就任されたら、自分で仕事を創造し、自分で人脈を育て、自分でケージに投げかけて、実績を上げ続けて生き残るようにしてください。多くの方が勘違いされていますが、ここでいちばんやってはいけないこと、それは「待つこと」です。要は自分が何か相談された案件に力を貸す役割だという思い込みです。顧問という文字から受ける印象は確かにそうなのですが、待つことで生まれるものは何もありません。私どもTESCOは経験上いろいろなケースを見てきていますが、自分から動かない顧問はだいたい平均して1年以内に辞めていきます。どういうことかというと、顧問というポジションは多くの場合、社長をはじめとするトップの方々がその役割をつくります。経営者が「この人のこういう知見で力をお借りしたい」というポジティブなケースもあるでしょう。そうかと思えば「かつて取引上でお世話になったので顧問として一定期間お引き受けしないと格好がつかない」というようなポジティブとはいえない理由でお引き受けしている例もあります。そこで共通しているのは「現場は欲していない」ということです。実際に会社のオペレーションを担っている現場の管理職レベルでは顧問は必要ない存在です。むしろ邪魔になっているのではないでしょうか。
顧問という役割に就き、最初の1か月、2か月くらいは会社も本人も珍しいこともあり、顧問が会社に出掛けてミーティングを主催したり、会議に呼ばれたりします。そこでは「営業の開拓先を紹介してください」などと言われ、自分で実際に動いてみることもあるでしょう。しかし数か月が経ってみると、自他ともにそれほど顕著な業績が上げられないことに気づきます。そのうち顧問には以前来ていたような煩瑣な連絡が来なくなってしまいます。そうなると自分から会社に連絡を入れるようになります。「そろそろ打ち合わせをしたいのですが、いつが空いていますか」などと投げかけても、思ったように日程が上がってきません。「また連絡します」とか「その日は出張でおりません」といったような対応が続くようになります。顧問にも鋭い方や鈍感な方がいらっしゃいますが、数か月経つと大なり小なり「自分は会社にそれほど求められていない」ということがわかってきます。そうなると関係は自然消滅し、1年の顧問契約で終了となるわけです。もちろん最初から1年で辞めたかったという場合は何の問題もないのですが、おそらく顧問に就かれる方は年齢もそれなりに高い方が多いでしょう。なるべく長く活躍して後輩たちの役に立ちたいとか、社会とのつながりを密にして本人も充実した仕事をしたいとか、そういう人が多数派ではないでしょうか。
多くの場合シニアは1年でも長く仕事をしたいというのが本音です。ところが会社は1年だけなら面倒を見てもよい、くらいに思っています。すなわち双方の思惑が異なるわけです。会社は顧問に対して「あまり余計なことをされても困る」と思っているので、結局「取引先を紹介してください」というような営業販路開拓の顧問のような肩書を与えるわけです。それでもし実績を上げてくれたら儲けものというスタンスになります。しかし現場がこうで、問題がこうだから、こういう取引先と商売したら会社にとってプラスです、自分がその端緒を作るのでみんな一緒にやりましょう!というところまでやらないと顧問だと認知されません。どこそこの誰さんを知っているので紹介します程度では現場としてもコミットメントできないので、顧問は徐々に忘れられてしまうのです。
今の時代の顧問というのは、自分で会社の問題や課題を自分からリサーチして示し、トップにプレゼンをして「こういうところが見受けられるから、こういう風に問題を解決するべきです」と提案することが必要不可欠です。言われたことにジャッジするのではなく、自分から仕事を創造して、経営陣に課題を認識させ、更にプロジェクトを主宰するということ。ここまでが求められるわけです。
いかがでしょうか。これでは顧問ではなく、まるで管理職の鏡のようなイメージで、違和感をお持ちになる方もいらっしゃることと思います。ですが現場としがらみのない顧問といえども、このくらいの動きをしなければ経営陣はともかく現場には認知されないのが現実です。現場を早く動かさないことには顧問も思い描いたような腕を振るうことができません。昔ならいざ知らず、今の時代における顧問やアドバイザーの役割は、そういった行動が真髄であるということをぜひ認識していただきたいと思います。これは多くの個別にお会いした方から反響が多いテーマです。特にシニア人材の方にとっては切実な問題ですから今後、機会があれば具体的な事例などを織り込んでみなさまにご紹介していきたいと思います。